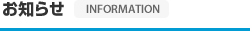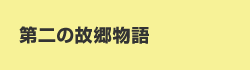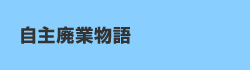シニアが心のハリを感じながら生きるには?
高齢者が増えている。日本は超高齢化社会を迎えている。今後高齢者を支えるためのさまざまなサービス、制度が生まれてくるだろうが、課題となるのはコストと人材だ。この面でも二極化が進んでいくのだろうか。北欧の場合、手厚い社会保障で、高齢者になっても老後の不安は少ないようだが、日本の場合はどうもそうはいかないようだ。孤独老人の孤独死も最近はニュースとして取り上げられることもあまり無いが、依然として増えているのではないだろうか。人は生きてる限り、いや生かされている限り、生きなければならない。しかしある場合には「生きることは死ぬより辛い」こともある。日本の戦後を奇蹟的な復興に導いたのは現在の高齢者だ。私達はこのことを忘れてはならないはずだ。ただ日本的経済成長は3つの点で大きな問題を抱えていた。一つ目は建設国債という名目で赤字国債を発行し続けたことだ。産業の発展のためにはインフラの整備は欠かせないが、この国債は建設主導型の経済構造を日本にもたらした。二つ目は日本の農業について適切な、持続発展が可能な道筋を見出すことができず、政治的に利用し続けてきたことだ。先進国で自給率がこんなにも低いのは日本だけだ。敗戦国として同じような試練の道を歩んできたドイツは自給率が100%を越えている。三つ目はコミュニティ、日本的に言えば「世間」の崩壊である。その結果、人を支える仕組みの「自助、共助、公助」の「共助」の部分は著しく損なわれてしまった。公助は自治体、政府によるサポートだが、財政改善の旗印の下、予算は削減傾向にある。一方自助の中には家族による助けも含まれているのだろうが、核家族化が進む今日、それも期待できない。残るは共助だ。どのようにして共助の仕組みをつくり上げていくか。これが戦後70年、日本に与えられた重要な課題の一つではないだろうか。